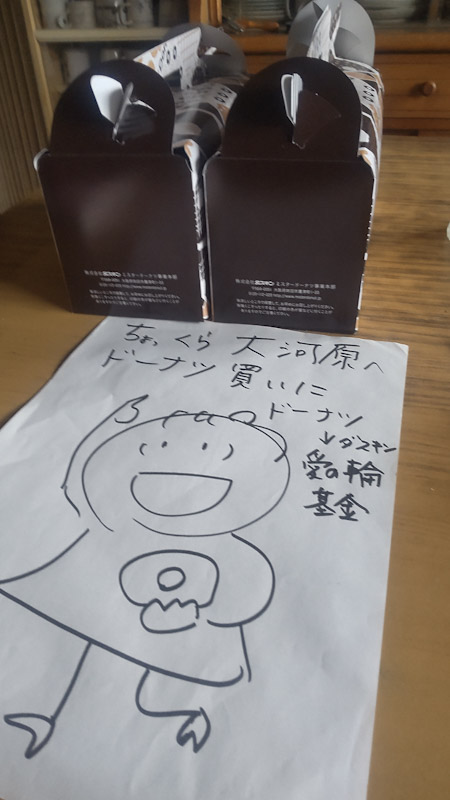

あまり でかでかと ポスターが貼ってあるわけではない
ダスキン愛の輪基金 ドーナツの日
わたくし ろくすっぽ 掃除もしねぇくせに
ずっと 4週に一度 化学ぞうきんを 交換に来てもらってる
それは ちちはは 掃除をまめにしていた時代からなのだけど
ダスキン配達を務めていた方が ばあちゃん実家に出入りしていた 由縁ある方で
ちちはは 掃除に 携われなくなっても
ご縁ある方だから と 辞めずに続けていた
そして その方が 病を得て 退かれたのち
節約のためもあって やめちゃうか と 思ったものの
引き継がれた方に 一度お目にかかったら
なんだか ものすごく 気持ちが明るくなるような お人柄で(多くを喋ったわけではないのだけど…声質とかもあるのかなぁ)
なんか 絆(ほだ)されたみたいな気持ちになって
続けている
ドーナツの日を知ったのも
その 月イチ 取り替えのときに いただく リーフレットみたいなものがきっかけだった
映画監督の 今村彩子さんが ダスキン愛の輪基金の リーダー育成事業で アメリカの手話を学びに ゆかれた とか も きいて
そういう 活動をしているところは 応援し続けたいものだ と 思ったりもしたのだったな
それよか 掃除もちゃんとしろよ なんですけど
動線を 箒で ちゃちゃ…と 掃くくらいしかやってない
わはは
んで ドーナツですけど
買った後 差し入れにも行くはずが
差し入れ先 不在
…あれ 通院日だったんかな?
とか もにゃもにゃしてたら
何度も通ってるはずなのに
またもや 道を間違え
「しぱぱっ と 早く帰ってくるよっ」と 書き置きして出かけたのに
2時間近く 母を待たせてしまいました…とはいえ
うたた寝してて わたくしが出かけたこと 忘れていたようでもあり
何事もなくてよかった
…で こんなに どうすんのよ ドーナツ
まぁ 甘いのばかりでもないので(食事っぽいやつ…でも ちょっと 甘く感じる) 食べられるけどさ
しょっぱいもんも食べたくなっちゃうよな と
賞味期限が どちらも 4日ほど過ぎている ちりめんと 豆腐で ドーナツ型の ぱりぱりを こさえてみる
ドーナツお揃いにしたわけじゃなくて
うちのマイクロウエーブが どうも真ん中を 熱してくれないようなのですわ(ご飯せんべいをこさえる時 必ず 真ん中が ふにゃふにゃのまんまになるの)
なかなか んまいわ♪
いちどに 食べきらないように 注意

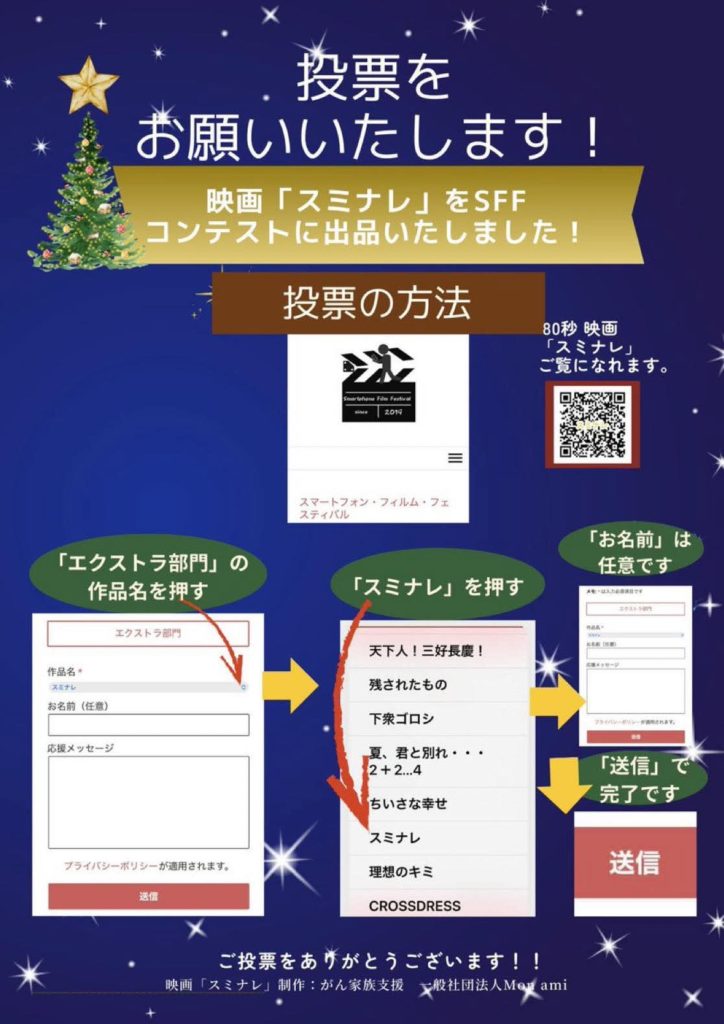
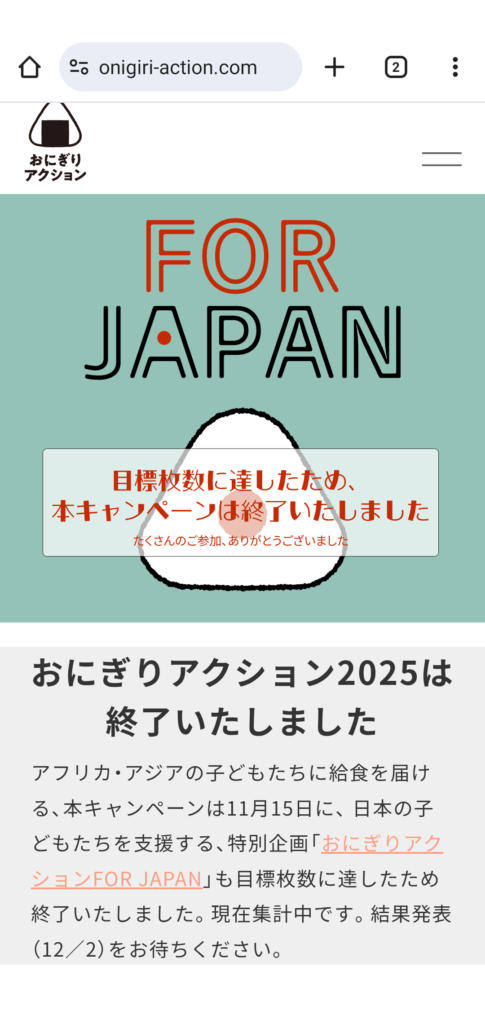




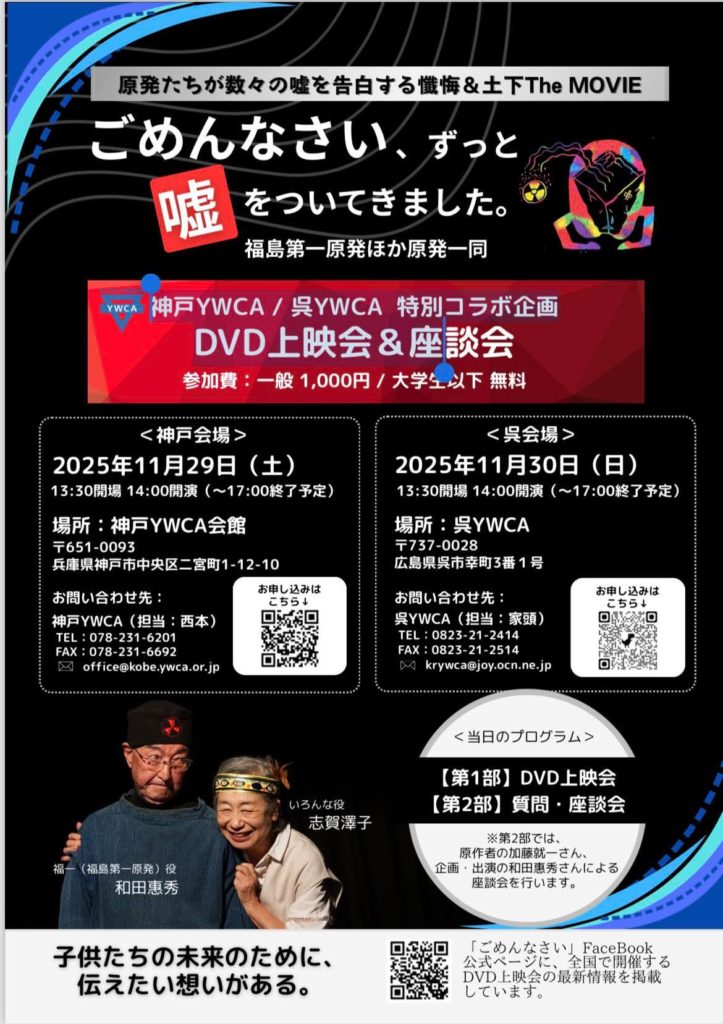

最近のコメント